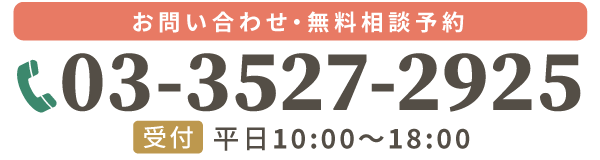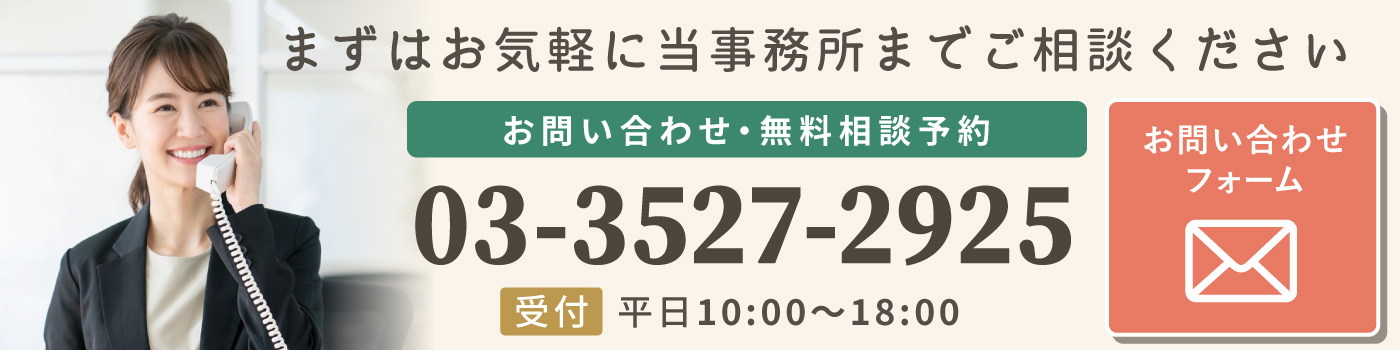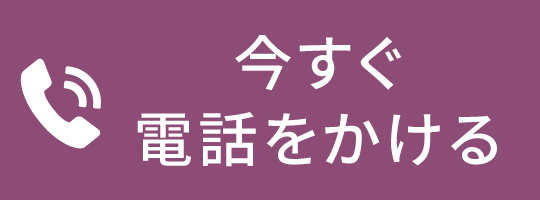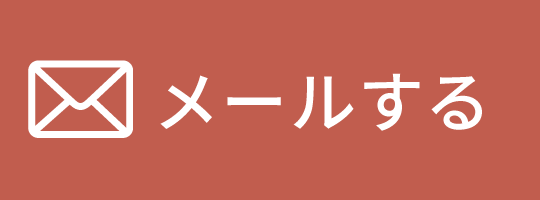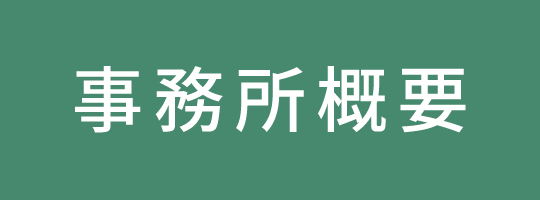みなさんは「相続時精算課税制度」という言葉をご存じでしょうか。
「相続時精算課税制度」とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税
の制度です。
相続においては、相続人が亡くなってからでしょうと考えておられる方もいらっしゃる
かもしれませんが、平成27年1月1日以後の相続においては、基礎控除が3,600万円+法定相続人×600万円となり、今まで相続税に無縁であった方も相続税申告の対象になってしまう例も出てきました。
資産形成における世間の動きに合わせて、相続における相談においても年々関心が高まっており
私の事務所も相談件数も増えてきております。
財産をお持ちの方が生前に行える相続対策として挙げられるものとしては、
①生前贈与
②生命保険への加入
③不動産の購入
④資産管理会社設立
⑤相続税試算(株価評価)
などがあります。上記内容を確認した上で遺言書などを作成したり、家族への思いを直接
伝えたり書き記したりされることで、ご自身の円満な相続を行うことができます。
税理士の立場としては、その思いがより形になることはもちろんですが、生前に行っておく方法如何により相続時における納税額を予測しより相続をスムーズにするという一面もあります。
冒頭にお話しした相続時精算課税制度は、端的に言うと2,500万円までは無税で贈与を行える制度です。
メリットが多い制度ですが、適用するための手続きがあったり、ケースにおいてはデメリットも存在します。
デメリットにおいては、
①暦年課税に戻せない
②財産の評価が下落する場合には余計な税金を支払うことになる
③小規模宅地等の特例が使用できない
などです。元々相続税申告においては厄介な上に、その相続において活用した方がよいはずの各種制度が難解であるがために、結果として専門家を活用した方が確実といった事になってしまいます。
ちなみに贈与税においての申告も贈与が行われた翌年の3/15日が期限となっており、所得税のみの申告と思いがちですが、我々税理士の世界では当たり前に贈与に関しての申告や納税の手続きが行われています。
相続時精算課税を検討している方がこのコラムを読まれていたら、手続きが必要であり、それについては期限があることも押さえておく必要がありますね。
また令和6年1月1日以降、この相続時精算課税制度を活用する上で、我々納税者に有利になる改正も行われています。(暦年課税の併用可)
相続にお困りの方はもちろんですが、そろそろご自身の相続が気になりだした方などは、一度税理士へ相談されてみてはいかがでしょうか。


郷原会計事務所では、東京都や神奈川県、福岡県をはじめとする関東・九州エリアを中心に、法人のお客様に向けた会計・税務サービスを行っています。上場企業から学校法人、社会福祉法人まで幅広く対応し、「関わる全ての人を幸せにする」という思いを大切に、お客様に寄り添ったサポートを心がけています。