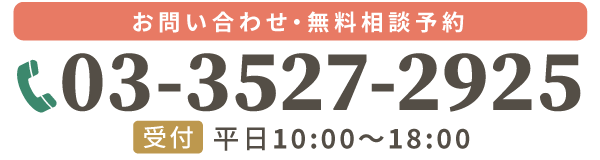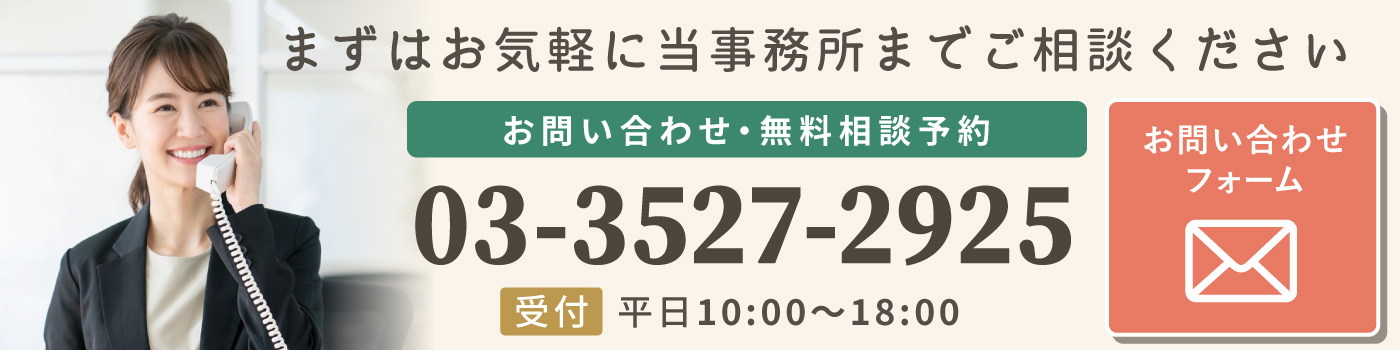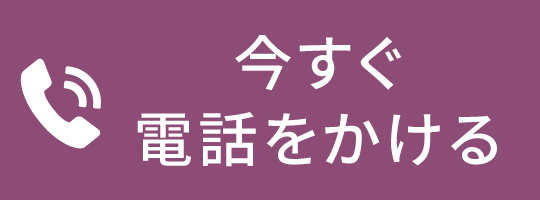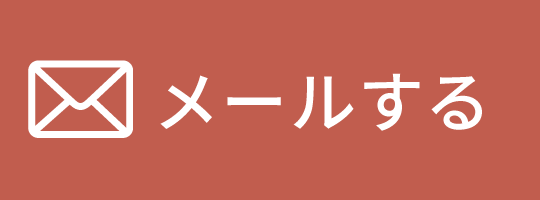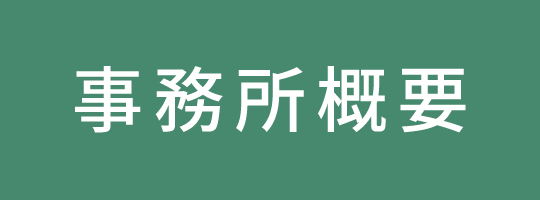令和7年3月27日に「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について」が公布されました。これは、学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年9月30日公布)で説明されている内容について、注意すべき点などについて書かれています。
いくつか論点がありますが、ここでは引当金に焦点を当てて説明したいと思います。
そもそも引当金においては、将来(来期以降)にい発生する可能性が高い支出に備え、あらかじめ計上しておくべき見積金額の事です。この引当金においては、企業会計原則注解において、4要件を満たしているものが引当の対象とされ、その年度に帰属する金額を費用として計上し、引当金が貸借対照表の負債に計上されます。ちなみに4要件とは以下のものになります。
・将来の特定の費用または損失であること
・発生が登記以前の事象に起因すること
・発生の可能性が高いこと
・金額を合理的に見積もることができること
まずは引当金についての説明をした上で、今回の改正に伴う論点として、引当金が注目される点について説明したいと思います。
従来の学校法人会計基準においては、各種引当金のうち、退職給与引当金、徴収不能引当金が主な引当金として計上されることを求められていました。というよりこの2つのみの計上以外をあまり認めていませんでした。
理由としては、損益重視している企業会計に比べ、資金会計を重視していた学校法人会計において一時的に大きな支出を伴う退職金や、収入の核となる納付金の焦げ付きに係る徴収不能における備え以外は収支に適さないという考えがあったようです。
一方で、引当金の本来の要件を考える上で、それ以外の引当金についても4要件に該当するのであれば当然に計上すべきという考えはいつも上がっていましたが、慣例として計上されることはほぼなかったと言えます。
ですが今回の改正では、会計基準第11条第2項において、引当金として要件に合致するものは計上すべきとの見解が出されました。そのため、会計に比較的明るい方はこの条文から、賞与引当金の計上をしないといけないのではないかとの流れになったのです。
パブリックコメントでは賞与引当金という具体的な名称も出ていましたが、国としては各種引当金が4要件に該当する場合には、個別の引当金に限定せず計上すべきとしています。
令和7年度決算において、引当金を設定した場合の処理方法も示されましたので、各種引当金を法人で計上する場合、引当金の種類、計上すべき金額の計算方法や計上金額、そして計算書類に計上すべき科目などしっかりと決算までに税理士や公認会計士などと打ち合わせを行い、決算時に慌てないようにしましょう。


郷原会計事務所では、東京都や神奈川県、福岡県をはじめとする関東・九州エリアを中心に、法人のお客様に向けた会計・税務サービスを行っています。上場企業から学校法人、社会福祉法人まで幅広く対応し、「関わる全ての人を幸せにする」という思いを大切に、お客様に寄り添ったサポートを心がけています。